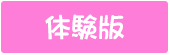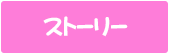ストーリー
プロローグ
子供への虐待や育児放棄、いじめが深刻化した近未来、政府は厚生労働省の外局として「人権庁」※1を創設。
その人権庁は傷ついた子供の心のケアを行う施設を新設する。
ここ、国立児童療育・保護センターもその一つであった。
生まれつき理由あって他人が当たり前のように出来る事が何一つできない少年、夢見コウタは学校でいじめられ、更には両親からは出来損ないと虐待され精神を病み、心に傷を負っていたが、人権庁捜査部※2に保護され、国立児童療育・保護センター※3に入る事となる。
そこでコウタは自分に生まれつきのハンディがある事、そして自分が背負った心の傷が根深い事を医師に告げられ、ハンディを克服する為の療育と傷ついた心のケアを受ける事となった。
コウタの心のケアを担当するのは人権庁・児童奉仕団※4の少女達……
彼女達から生まれて初めて人に優しくされる経験を受け、次第にコウタの心の傷も癒えていく。
しかし、コウタは知らなかった。
児童奉仕団の少女たちの間ではおむつを着用して愛撫しあう、おむっくすという淫らな遊びが行われていた事を。
そしてコウタも少女達によってその淫らな集いへと誘われていく……
用語集
※1 人権庁
深刻化する子供への虐待や育児放棄、いじめから被害者を迅速に救済する為に設立された厚生労働省の外局。
管轄が厚生労働省なのは被害者のケアに専門の医療施設を設置する必要があった為である事と、特にハンディを持つ子供への虐待率が高い事情がある。
※2 人権庁捜査部
子供への虐待や育児放棄、いじめの被害を捜査し、被害者を救済する為の措置を実行する組織。
虐待通報アプリ等を通じて虐待被害を収集・捜査し、子供達を救出し必要があれば専門の医療機関へ引き継ぐ業務も行っている。
虐待については被害児童の家に突入する為の突入隊(SWAT)も課内に存在する。
※3 国立児童療育・保護センター
虐待やいじめの被害で心身に傷を負った児童を保護する医療施設。
なお、これは通称であり、同様の施設が全国各地に設置されている。
保護された子供がハンディを持っていた場合、療育が必要なため、療育施設としての機能も持っており、この名前で呼ばれている。
※4 人権庁・児童奉仕団
国立児童療育・保護センターで心に傷を負った子供の心のケアを行う児童ボランティア組織。
人権庁の公募から応募した者のうち適性のある児童が選ばれている。
年代記
社会史講義録:大石事件から人権庁創設まで(2094–2101)
第一章 停滞の十六年――「成長率負の連鎖」の実相
国家経済の成長率が16年連続で悪化するという、近代統計においても稀な長期停滞が始点である。雇用は細り、賃金は硬直し、可処分所得はじわじわと削られる。
税収は伸びず、インフラ更新は先送りとなり、地方は空洞化。
――この負のスパイラルは、やがて家庭に侵入し、育児・教育・保健・福祉のあらゆる継ぎ目を軋ませていく。
学術界はこれを“家庭の脆弱化”と命名した。
第二章 国会、沸騰す――「大石事件」発火点(2094)
これを与党が拒否した瞬間、委員会室の空気は沸点を超える。
木村勝雪首相に大石が掴みかかるという異例の物理的接触。
議場は紛糾、衛視が奔走、与野党応酬、記者団一斉フラッシュ――この事件は後に**「大石事件」**と呼称される。
街は呼応した。木村内閣に退陣要求の大規模デモが各地で連鎖点火。
“秩序は静かに崩れるのではなく、怒りの可視化によって臨界を超える”――政治学者・青葉錦三の言葉が引用され続けるのは、この日からである。
第三章 不可視の悲鳴――松下書簡事件へ(2096–2097)
その原因として経済悪化による国民のQOL低下があるとして因果関係を示し、児童相談所・保護施設の増設と人員強化を要請するも、内閣は財源上の理由で拒否。
同年12月、吹雪が吹き荒れる中、首都某所で裸の少年が家から締め出され警察は保護。
児相へ送致されるが、「差し迫る危険なし」と判断され自宅へ還送。
そして翌年1月3日――少年は庭で首を吊り自殺。
遺書は淡々としていた。
「長期の虐待」「児相は動かなかった」。
東西日報・社会部の若手記者、松下敬太が遺書の存在を報じ、行政の判断基準の硬直が炎上点となる。
担当所長は「対応に問題なし」と発言。
市民は膝から崩れ落ちるような徒労感を共有し、やがてそれは制度解体論に収束。
以後、この一連の事件は**「松下書簡事件」**として歴史項に刻まれる。
記者倫理と公益通報の境界線を大きく押し広げた。
第四章 選別と偏り――首都圏キッズ食堂問題(2097・夏)
欠食児童へ食事の無償提供を続けてきた良心の象徴、その実態は女児にのみ食事を提供、男児には“頑張って”と励ますだけで追い返していた—――この性別選別が内部告発で露見する。
代表の長倉夢芽は国会招致で「支援選択権は団体にある」と応酬。
政府補助金の透明性、セーフネットの恣意性、ガバナンスの欠落が一気に俎上へ。
議場は熱を帯び、制度の再設計が論じられるが、具体法案は不発。
ここで政治の決断能力の空洞が国民の眼前に露呈した。
第五章 新旗の掲揚――自由国民クラブの登場(2098・1)
新党**「自由国民クラブ」**を結党し、ダブル選挙へ突入。キーメッセージは二つ――
・長期不況からの離脱には大規模財政出動が必要不可欠
・児童虐待・ネグレクトは国難である。
TV、誌面、SNS、路上演説、全方位の浸透作戦。支持は雪崩のように動いた。
第六章 主権構造の再配線――憲法改正と権力形態の移行(2098・4)
有栖川はただちに憲法改正を掲げ、「国家の迅速な意思決定」を至上命題化。
国民投票は同日実施という電撃手法、賛成80%で可決。
国家体制は首相制から権限強化型の大統領制へ移行。批評家は「近代以降、最短の主権更新」と評した。
第七章 連続する大統領令――経済と行政の地ならし(2098・5)
大統領令第二号:これに抵抗した一部官僚勢力の懲戒免職。
有栖川は「意図的成長阻害」として断罪。行政は遂行組織へと再定義される。
――是非の論は続く。
だが、歴史は記す。意思決定の速度は、このときたしかに加速した、と。
第八章 人権庁の創設――分散の終焉、一本化の開始(2098・5)
「家庭内暴力・児童虐待・ネグレクト――既存の児童相談所も、民間福祉NPOも、十分な救済能力を有していない」厚生労働省の外局「人権庁」を新設し、被害者保護施設を全国に展開。既存の児相・福祉NPOは解散、業務は人権庁に一本化。――これが大統領令第五号である。
賛成意見:責任の所在を明確化し、救出→保護→療育をワンストップ化する必要。
第九章 執行の腕――人権庁捜査部と福祉部(2099)
捜査部:警察権・捜査権・逮捕権を付与。通報受理→実地調査→緊急保護→逮捕・送致までを一気通貫。
福祉部:保護施設の運営、衣食住の確保、医療・心理のトリアージ、就学・就労の中継。
さらに人権庁福祉団――医師、カウンセラー、弁護士、学生ボランティアを束ねる民間協働部隊が編成される。
ここで光るのが中間管理の匠たちである。
- 唐島真澄(捜査部・統括監):夜間緊急対応の標準手順“K-7プロトコル”を設計。通報から90分以内の物理保護率を**68%→91%**に引き上げた。
- 楊谷(やなぎや)巡査部長出向:虐待現場での加害親の武器化(刃物・火災・車両)に対し、非致死制圧4点セットを導入し負傷率を半減。
- 湊田ちなみ(福祉部・ケースワーカー):保護直後の沈黙期に対する**“聴かない傾聴”**手法を定着させ、自傷率を抑制。
第十章 療育への収束――国立児童保護・療育センター(2100)
「先天性障害のある子どもは虐待リスクが健常の4倍」
人権庁は福祉部の施設を増設**「国立児童保護・療育センター」を各地に設置**。
療育と保護を併走させる二層フロア設計(赤ラベル=急性保護、青ラベル=長期療育)を導入。
リハビリ+学習支援+社会復帰プログラムが一本のラインに接続される。
第十一章 制度の影――抵抗・逸脱・再統合
懲戒免職となった元官僚古賀和臣は学術誌で告発論文を発表。
「集権の暴走」と題したそれは、統制強化の副作用――現場裁量の縮減を突く。
他方、現場では**基準の“硬さ”が再燃。「連れ戻しを望む児」**の取り扱い、加害親の更生意欲の査定、里親へのインセンティブ設計――曖昧さが必要な領域が確かに存在した。
この時期、人権庁は第三者監査局を増設。外部監査に当事者経験者(元被保護者)を入れ、制度の内側からの評価を開始する。
“完全な制度は存在しない。だが、学習する制度は作れる”――監査局長佐伯祐真の言。
第十二章 小さな歴史――夢見家の記録(2101)
奈緒子は数年前に人権庁の緊急保護で救出された当事者であり、療育センターの長期プログラムを経て社会復帰していた。
出産届の付記欄には、迷いのない字でこう書かれていた。
「明るい未来をプレゼントしたい」
そして10年後……
この物語・ゲームはフィクションです。
実在する人物・事件・団体とは一切関係ありません